
| 2012/04/13 スポーツ傷害について(第2弾)~怪我はどうやって防ぐ?~ |
第2回目のコラムはスポーツ傷害について(第2弾)~怪我はどうやって防ぐ?~です。前回少しだけ紹介した怪我の発生要因にてまずは説明します。下の図が怪我の発生要因です。 発生要因には、個体要因・環境要因・トレーニング要因の3つがあります。
個体要因とは、その人個人の体の構造や機能に関するもので、筋力や柔軟性、スキルやスポーツ動作の特徴などがあり、これらの要因が怪我をしやすい体であったり、怪我のしにくい体であったり、その人個人によって変わってくるものとなります。
環境要因とは、スポーツを行う上での環境や使用する道具に関するもので、その時の天候やグラウンドコンディション、その時に使用していた用具の状態などを表します。晴れた日や雨の日、暑い日や寒い日では体の調子も変わってきます。そして、使用用具としては、シューズなどの重さや擦れかたにより、パフォーマンスの違いやコンディショニングにも変化が生まれます。
トレーニング要因とは、スポーツそのものの実施内容に関するもので、運動の種類や負荷量、競技種目によっても変化があります。よくある例でいえば、いつもよりトレーニングや試合の頻度と負荷量が多く、オーバーユーズの状態になり怪我をしたりというような事がよくあります。
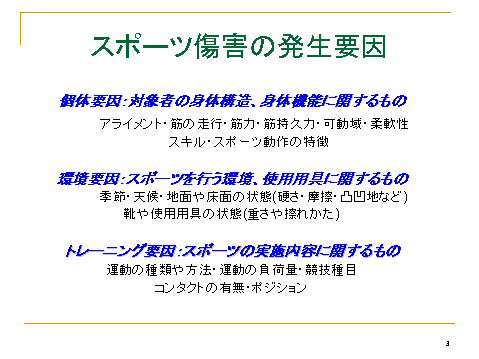
それではこれらの発生要因は、どうすれば予防できるかを考えてみましょう。
まず個体要因に対して出来るものとしては、生まれつきの骨の形態や筋の走行などは自分で改善できるものではありません。しかし、柔軟性や筋力に関しては改善できるものです。運動前のストレッチや準備運動だけでも運動中や運動後に個体にかかる負担は変化します。
下のグラフは、部活動を行う約200名に向けてアンケートをとった結果です。部活動を行う前に必ずアップをする学生は半分以下の42%となりました。また、私が驚いたのはアップをしない生徒と、たまにしかアップをしない生徒を足すと約15%もいることです。その理由としては、時間がない、アップをしてもしなくても変わらない気がするなどといった返事が返ってきました。アップをなぜ行うのか、そしてアップを行った時の利点やアップの種類など、アップに対しての知識を指導しなければいけないと思います。なので、アップの目的を理解することが傷害予防にも繋がってくるのだと感じました。今後のコラムでアップダウンの目的と方法については掲載していく予定です。
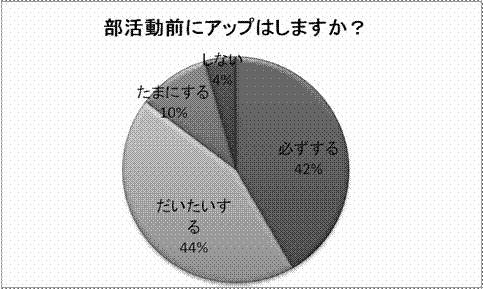
次に環境要因に対して出来るものとしては、天候やグラウンドコンディションはなかなか改善できるものではありません。しかし、道具の状態などは自分でチェックできるものです。靴の擦れ具合や使用している道具は、チェックしていますか?靴がすり減った状態でスポーツを行うのは滑ったりして危険なのはもちろんですが、滑らないように気を付けながらスポーツを行う事により、自分の普段どうりのパフォーマンスが行えず、無駄な筋力を使うことにより、本来のフォームを崩し、その崩れたフォームを繰り返し行う事により傷害に繋がります。このことについても今後のコラムで説明していく予定です。
次にトレーニング要因に対して出来るものとしては、日頃の練習で行っている筋力トレーニングや自分のフォームは正しく正確なフォームで行えていますか?何も意識せずにただ何となく回数をこなしていたりしていませんか?そのことが大きくスポーツ傷害に繋がっています。たとえばその日の自分の状態や疲労具合を考えずにいつもと同じようにトレーニングなどをしていませんか?誤ったフォームで筋力トレーニングを行ったり、疲労などを考えずにただがむしゃらにトレーニングを行う事により、一部の筋肉を強く損傷したり、疲労が溜まった状態で行う事によりフォームの崩れが生じ、そのまま繰り返しの動作で傷害を発生させることにもなります。正しいフォームでしっかり意識して筋力トレーニングや普段のプレーを行う事により、パフォーマンスの向上に繋がるのです。このことについても今後のコラムの中で適切なトレーニングの仕方や、簡単な野球の投球動作についての説明を掲載していく予定です。
さて今回のコラムはいかがだったでしょうか。今回は軽くさわりの部分を説明しました。次回以降で詳しく様々な面から説明していきたいと思っております。
今後のコラムでこのような事が聞きたい!こんなのはどうですか?などの質問・ご意見お待ちしております。問い合わせのメールフォームからお送り下さい。
次回のテーマはアップとダウンはなぜ行うのか?~ストレッチの目的と効果~です。次回もよろしくお願いします。
|

|
|
|















